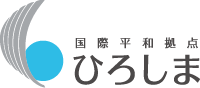【白球を追いかけて】うえむらちか

8月6日。
日本にとって特別な日。
そして、広島にとっては忘れ得ぬ日だ。
午前8時15分、街中はサイレンに包まれる。毎年鳴っている黙とうの合図。上京した時はサイレンが鳴らなくて少し戸惑ったことを覚えている。
私の祖母は15歳の時、女学校へ向かう通学途中に被爆した。つまり私も被爆三世ということになる。体験したことのない人にとって、戦争はどこか遠い世界の話に思えるけれど、実はすごく、本当にすごく身近な話なのだと思う。
ただ、私は小さい頃にその話を聞いて、堪らなく恐ろしくて、深く知ろうとしなかった。けれど大人になって改めて当時の話を聞いたとき、「なぜもっと早く聞いておかなかったんだ」と、その判断を強く後悔したことを覚えている。
それから私は何度も祖母の話を聞いて、当日の祖母の行動を仔細に書き起こした。
今から皆様に読んでいただくのは、あの日、祖母カズヱの身に起こった8月6日の記憶である。
祖母の記憶
一九四五年八月六日。
雲一つない、抜けるような青空の下、眠たい目をこすりながら、セーラー服にもんぺ姿の少女がひとり、同級生の家へと向かっていた。
昨夜から何度か空襲警報や警戒警報が発令されていた。今朝も七時九分に警戒警報が発令していたが、三十一分には解除された。
同級生の大半は勤労動員されていた。この日も安田高等女学校の生徒は、大橋工場、誉航空軽合金、高密機械製作所、興亜密針々製作所、中島地区の作業に緊急動員されていたものも合わせると、八百人以上の生徒が働いていた。十五歳の少女――カズヱも何ヶ月か軍需工場に出動したが、途中で血液検査に引っかかり、身体虚弱要保護生として通年動員を解除され学校へ戻された。残留組と呼ばれた。特段身体が弱いということがなくとも、連日の激しい勤労と不十分な食糧事情による栄養失調で脱落していく者が出始めていた頃だった。六十名余りがいた。皆が働いている中、学校へ戻るのは気兼ねしたが、カズヱたちはその間、校内運動場に作った芋畑を耕したり泉邸(現・縮景園)の掃除などを任されたりしていた。
午前八時。学校へ向かう途中、友達を迎えに行くために広島駅から猿猴川の川沿いに立ち並ぶ同級生宅に立ち寄った。二階建ての豪邸で、家の中にはオルガンもあった。この豪邸の持ち主は、地元でも有名な梅肉エキスを売る築田三樹園社の築田家で、築田家に嫁いだ姉と一緒に、カズヱの同級生である妹の梅本美和子もここで暮らしていた。
「カズちゃん、おはよう。照江はもう来とるよ」
美和子の支度を待つ間、先に到着していた渦巻照江と共に二階で待たせてもらうことになった。窓辺に置かれた椅子に照江と二人、腰掛けていた。カズヱは、この部屋の主人としてデンと鎮座しているオルガンが好きだった。この日も、美和子を待つ間オルガンを見つめていた。窓辺に背を向けて。これが運命の分かれ道になるとも知らずに。
八時十五分。
ふいに、視界一面に黄色い光が広がった。
それがなんであるのか考える余裕もなかった。轟音と共に叩き付けるような衝撃が駆け抜けたかと思うと、目の前が真っ暗になった。一瞬にして建物の屋根が崩れ落ちてその下敷きとなった。
気が付くと辺りにあったのは残骸だった。それまで屋根や柱の一部だったものが無数の焼け焦げた木材と化して周囲に積み重なっていた。雲一つなかった青空は消え、空はまるで昼と夜のスイッチが切り替えられてしまったかのように黒煙で塗り潰されていた。
何が起こったのか分からなかった。一瞬にして世界がひっくり返ってしまったかのようだった。カズヱの背中には無数のガラス片が突き刺さり、その両脚は太股から指先まで皮膚が爛れ、まるで自分のものではないかのように赤黒く腫れ上がっていた。恐怖に駆られながらも何とか瓦礫から這い出た時、まるで風船のように顔が膨らんだセーラー服の少女の立ち姿が目に入った。
「あんた誰?」
カズヱはそう口にしかけて、はっと息を呑む。
それが色白でべっぴんさんと評判だった美和子の変わり果てた姿と気がついたからだ。爆心地から約一・五キロの出来事だった。
誰も何も分からぬまま外へ出ると、全ての建物は倒壊し、瓦礫の山が出来上がっていた。辺りには嗅いだことのないような異臭が漂っていた。
「東練兵場に行こう」
築田一家と照江と共に足を引きずって、およそ一キロ離れた広島駅の裏手にある東練兵場へと向かった。街の中はあちこちで火の手が上がっていた。家屋の焼け落ちる、バリバリ、バリバリ、という音が悪夢のように鳴り響いていた。途中、大須賀踏切の上で親子が倒れて死んでいた。母親が子どもをかばうように覆い被さっていた。美和子の顔と同じように、いや……それ以上に赤黒く膨らんだ顔だった。
東練兵場の塀まで辿り着くと、梯子が掛けられているのが目に入った。すでに誰かがここを越えていったのだろう。カズヱたちもその梯子を使って中に入った。東練兵場は軍隊の練習場として使われていた場所だ。そのため広大な敷地の中にはぞろぞろとたくさんの人が避難してきていた。しかし、その大半は皆、衣服も着けていないようなボロボロの有り様で、それどころか服だと思っていたものは垂れ下がった皮膚片だった、という者もいた。この場所には兵隊に助けを求めようと来た者もいるだろう。しかし、ずらっと並んだ兵隊はみな地べたに座り、上を向いて「あ……」「あ……」と声にならない声をあげていた。
練兵場に積み重なってあった枕木は、熱波で燃え上がり、人々はただそれを呆然と見ているだけだった。
すぐ隣にある東照宮の麓へと移動する。
腰をおろすと全身の猛烈な痛みに襲われた。今まで麻痺していた神経が一気に戻ったかのようだった。照江と肩を寄せ合って、必死にその痛みに耐えた。
日が暮れて辺りが暗くなってくる。
声が聞こえてきた。
「水が飲みたいよ。水が飲みたいよ。兵隊さん、水飲ませて」
カズヱと同じくらいの若い女性の声だった。それは次第に小さくなっていき、最後には聞こえなくなった。
(夢じゃ……)
一睡も出来なかった。
停電で真っ暗な世界が広がる中、全てを焼き尽くすように赤い炎の光だけが市内から煌々と闇夜を照らしていた。カズヱはじっと目をつむって、これは夢だと自分に言い聞かせた。
朝日が昇ると、眼前に広がっていたのはまさに地獄そのものだった。
何百人いるのだろうか。広大な練兵場には、少し動くだけで隣の者と肩がぶつかってしまうくらいの人で溢れかえっていた。
その全てが異様な空間だった。
顔が真っ黒に腫れ上がり、目も鼻も分からなくなった者、唇が脹れ上がってコッペパンのようになってしまっている者、目玉が潰れて瞼が鶏卵のように腫れ上がった者、手足から皮膚を垂れ下げながら幽霊のように歩く者。声を出すことができなかった。目を背けたくなるようなこの世の終わりの光景がそこには広がっていた。
昼まで待ったが、家からの迎えは来なかった。カズヱは自分の足を見る。赤黒く焼け爛れ、感覚もなくなった二本の足。ここまで歩けたことが奇跡のようだった。とても十キロも離れた自宅まで辿り着けるとは思わなかった。
父は迎えに来てくれるだろうか。私がこの場所にいることはわかるだろうか。カズヱの背中にはじんわりと嫌な汗が浮かんでいた。ひとりひとり息をしなくなる者が増えていく。
(このままここにいたら、死んでしまう)
途方に暮れて膝を抱えていると、ふいに聞き慣れた地名が耳に飛び込んできた。
「矢野の人はおらんね?」
自転車を押している年若い男性だった。帰りたい一心だった。
「います! ここにいます!」
言葉は考えるよりも先に空気を震わせていた。しかし、すぐに「あ」と、照江の顔を見る。美和子は家族と一緒だが、照江にもまだ迎えは来ていなかった。ここを離れてしまっては二度と会うことは叶わないのかもしれない。カズヱほどではないが照江も負傷している。カズヱが迷っていると照江は頷いた。
「帰りんさい。うちも絶対家族と会うけぇ。あんたも絶対家に帰るんよ。それでまた学校で会おうや。絶対よ」
学校が無事とは到底思えなかった。けれど今のカズヱたちにはそれが希望だったのだ。
自転車のハンドルの根本からサドルに伸びた上管部分に座らせてもらい、練兵場を後にする。男性が自転車を押しながら、練兵場を出発して六キロほど過ぎた辺り――船越町では救護所が設置されており、怪我人の対応に追われていた。市内からどんどん人が逃げてくるのだ。いくら手があっても足りないようだった。しかし、幸運にもカズヱは他の怪我人と一緒に手当して貰えることになった。包帯をぐるぐると、足も顔も包帯を巻いて貰った。
そうして約十キロ離れた農家の自宅にたどり着くと、カズヱはそのまま倒れるように意識を失った。家族は生死も分からなかった娘の生還に泣いて喜んだが、カズヱはそれさえも記憶にはなかった。
被爆から九日後、終戦を迎えるも、顔の右半分と下半身が火傷でただれ寝たきりであったカズヱには知る由もないことであった。

「あの日もこんな青空だった…」
あれから、78年目の夏。被爆地の大須賀町の河岸緑地を歩きながら、祖母が言った。
私に話してくれた忌まわしい記憶は、まるで昨日起こった出来事のように、今なお祖母の脳裏に深く鮮明に刻みこまれている。
大須賀の町の様子はすっかり変わってしまったけれど、そこから見上げる広島の夏空はあの日と同じ、だ。
祖母の心を救った『ソフトボール』
そんな広島の夏は、炎天下でボールを追いかけた、祖母の昭和の名プレーヤーとしての思い出も掘り起こしてくれる。
祖母の身体に刻まれた火傷の痕は、今では言われないと分からないくらい薄くなっていたし、背中に42年間も埋まっていたガラスの破片は手術で取り除くことができた。

しかし、時間が解決しない傷もあるのだと思う。
被爆後の広島では「原爆を受けた女性とは結婚するな」という噂が広がった。ましてケロイドを負った祖母は、いろんなものを諦めるしかない人生を送らなければならない、そう思っていたという。
そんな祖母の心を救ったのが『ソフトボール』だった。
戦後の広島で、祖母の通っていた安田高等女学校(現安田女子中学高校)の安田實教諭が「原爆で何もかも失った生徒らに、何か希望を見いだせるものをつくらなければ学園は再建できない」という強い想いから、ソフトボール部を創設したことがきっかけとなり、祖母はソフトボールを始めることとなる。

一度は焼け野原になった広島の街、原爆にあって大きな傷を負ったにも関わらず、ソフトボールとの出会いを通して、体と精神を鍛えて、スポーツに打ち込んでいった祖母。部内でも主将で4番という大役を任されることとなった。
それでも、最初のころは「女の子がスポーツなんて」と周りからは揶揄され、チームメイトは親から反対され、練習に参加できないということも往々にしてあった。

しかし、なぜ祖母たちは周りから反対されてまで、ソフトボールに打ち込むことができたのか?
それは、諦めることでしか折り合いがつかないと思っていた人生の中で、「スポーツを通して頑張ったことが結果になって現れたこと」−−その成果が祖母の生きる活力になったからだった。
毎日傷だらけになって、もんぺ姿に素手で白球を追いかけた。満足な道具もなかった。それでもなお、広島県内で初めて開かれた広島県下ソフトボール選手権大会では初優勝を飾り。祖母は決勝点のホームを踏んだ。
ソフトボールをやっている瞬間だけは、被爆を忘れられたという。

時代も状況もなにもかも私たちとは全く違う当時の状況。きっとその何百分の一であっても理解することは難しいのかもしれない。それでも、祖母の話を聞いていたら、どんな苦境の中でも乗り越えられないことは決してない、そう強く感じることができた。
祖母はその後、社会人ソフトチームにも誘われたが親の反対で諦め、21歳で祖父と結婚した。結婚して子どもができてからも、祖父とはよく野球を観に行ったという。ソフトボールで培った知識から、野球観戦が趣味だった祖父とは互いに熱心なカープファンになった。
そして、祖母が父を連れて球場に行き、また父が私を連れて球場に行く……。そうやって脈々と受け継がれていったものがある。
「野球」と「平和」
祖母からはよく「小さな大投手」と言われた長谷川良平さんの活躍を聞かされた。そして、祖父が亡くなった今でも、祖母の部屋からは野球中継の音が漏れてくる。
その音を聞きながら、野球が繋いでくれた絆が今も私に繋がっている、とそう感じることができるのだ。
「野球」と「平和」という一見かけ離れた存在が、私の中では切っても切り離せない、重要な結びつきで存在していた。

今年で16年目となった、核廃絶と平和を願う「ピースナイター」。
実は、カープの本拠地では、1958年シーズンを最後に、長い間8月6日には公式戦が開催されていなかった。そんな中、2011年8月6日に、53年ぶりの広島の地で公式戦が開催されるきっかけとなったのは、当時カープの主力選手として活躍し、現在は千葉ロッテマリーンズの二軍打撃コーチとして指導に当たっている栗原健太さんのブログの存在だった。
山形出身の栗原さんは、カープ入団後に広島出身の女性と結婚し、それから原爆の日を意識するようになったという。そして、広島市が規則で球場を「休場日」としていたため、8月6日は遠征や移動日で広島の地にいられないことに対して疑問を抱いてくれたのだった。
中にいるとわからないことを、こうして他県から来てくれた方が想いをもってブログで懸命に発信してくれたことによって、色んな人の気持ちを動かした結果だった。
そうして実った「ピースナイター」が、今でもこうして続いている。
戦後70年という節目の年には球場で半旗を掲げ、全員で黙とうし、カープの選手はすべて帽子に平和の象徴となる白い鳩。そしてセ・リーグでは初めてとなる全選手が統一の背番号「86」のユニフォームを着用して試合が行われた。
単に原爆の日に試合を行ったというわけではない。今も昔も、これからも。「カープ」という存在は、広島の戦後の復興を支えた希望の光だった。
そんな想いの上にできた「カープ」と、そして野球ができる「平和」に感謝して、今一度この希望に火がともる瞬間を、これからもずっと楽しみにしている。
そして、私は今日も白球を追いかける。

【Profile】
うえむらちか
広島出身。広島で生まれ育ち、現在も広島でテレビ、ラジオなど多方面で活躍中。2016年、Wacoal主催「Red Fashionista Award 2016」スポーツ部門カープ女子代表として受賞。2022年、第1回ひろしま国際平和文化祭公式サポーター。RCCラジオ『うえむらちかの鯉スル企画室』MCを担当。広島テレビ『ZIP!』月曜日キャスター、広島ホームテレビ『ピタニュー』コメンテータとして出演中。
この記事に関連付けられているタグ