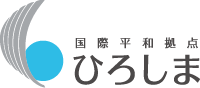Leaning from Hiroshima’s Reconstruction Experience: Reborn from the Ashes vol1コラム:医師たちの奮闘――未曾有の惨劇に立ち向かう
はじめに
「この広島におちたピカドン爆弾はふしぎだぞ。元気でピンピンしていたやつが急に死んだりするんだ。なぜだろう1)」―漫画家の中沢啓治は,その自伝的作品『はだしのゲン』のなかで,爆心地の原風景の一端をこう描写した。膨大な死者,瀕死の重傷者,そして一見健康そうな人の髪の毛が抜け,顔や体に赤い斑点が現れ,喀血しての突然死。ゲンたちが見ていた光景は,被爆した多くの人びとが目撃したものでもあった。こうした未曾有の異常事態は,治療に当たっていた医師たちにも強い衝撃を与えた。
1 戦争と医師
太平洋戦争の末期,米軍の空襲による市街の延焼を防ぐため,昭和19(1944)年11月から広島市内各所で建物の解体が始まると,市外に疎開する市民の姿も見られるようになった。広島県当局は空襲時の救護対策に支障をきたすことを懸念し,「防空業務従事令書」を発して医師の疎開を禁じた。かくて原爆が投下される直前,広島市内には298人の医師が残った2)。
2 医師たちの被爆体験
白島の自宅で被爆・負傷し,勤務先の広島逓信病院で縫合手術を受けた蜂谷道彦病院長は,原爆投下の翌日,昭和20(1945)年8月7日に,広島市西部の廿日市から病院に見舞いに来た部下から,市内の惨状を次のように聞かされた。「南は鷹野橋の辺りまで焼け落ちてしまって,赤十字病院の辺りからぽつぽつ焼け残った家があります。日赤は焼けとらん,宇品の方は焼け残っとる。日赤へちょっと行ってみたんですが,ここと同じことでさあ。病院の内も外も患者で一ぱいでさあ。あの前の電車通りは死人がずうとならべてあります。あの辺から御幸橋の辺りまで道の両脇に死体がまとめてあります。革屋町や紙屋町の電車の中には黒こげ死体がうずくまっています。あの辺の死体は黒こげが多いです。ビルの窓からまだ煙がでていますが,方々に黒こげ死体がありますよ。水槽の中に何人もはいって死んでいるのはむごいですなあ。逃げおくれた者でしょうて3)」。
部下の話は,病床にある蜂谷病院長の想像をはるかに超える凄惨さであった。広島では蜂谷のように多くの医師が被爆した。当時市内在住の医師298人の実に90%が罹災し,そのうち60人が命を落とした4)。健全な状態で救護活動を行いうる医師はわずか28人に過ぎなかった。歯科医や薬剤師,看護師も皆,同様に被災しており,傷病者の治療の任務に当たるべき専門家集団そのものが壊滅的な打撃を受けていたのである。
3 「原爆症」に対峙する
戦争中,空襲に備えて国民学校(小学校)に救護所を設ける計画であったが,市内の学校の多くがひどく損壊しており,それゆえ広島県衛生課は重症患者が多数集結した場所を仮設救護所と定めて,そこに救護要員と医薬品を送り込んだ。被爆直後に急設された救護所は53か所に上り,県内各郡の医療スタッフはもとより,山口や島根などの近隣県や大阪,兵庫など県外からも救護班が応援に駆けつけ,負傷者の救護に当たった5)。
市内の開業医がほとんど壊滅状態にあったため,負傷者たちは広島赤十字病院や広島逓信病院など大きな病院になだれ込んだ6)。医師たちは負傷の身ながら,自らの使命を果たすべく傷病者の治療に当たった。ただ被爆直後の混乱期,医薬品が欠乏しているなか,当初は赤チンや油による外傷や火傷の手当てにとどまり,十分な対応を取りうるべくもなかった7)。
そのうち,無傷で健康そうな人が突然死するという異常な現象が,病院の内外で見られるようになる。「広島のガスを吸うたら死ぬ」といった噂がすぐに市内を駆けめぐった。医師でさえ,米軍が毒ガス弾を投下したのでは,と錯覚するほどだった8)。広島赤十字病院の朝川貫之内科医長は,無傷の者が「何で死ぬるのか初めのうちはわからなかった」けれども,血液検査で白血球が激減している事実に驚愕する。急性放射線障害,いわゆる「原爆症」であった。同じ広島赤十字病院の重藤文夫副院長(広島駅の東口で被爆,頭部に負傷を負った)も,大学院時代から放射線医学を研究し,白血病患者の治療に当たった経験があったが,その彼をしてもすぐには目の前の患者の症状と放射線障害を結びつけることができなかった9)。広島の医師たちは,人類がいまだかつて経験したことのない「原爆症」に立ち向かうことを否応なく迫られたのである。それは「つねに,出遅れた,受身のたたかい10)」であった。
おわりに
広島市内にいた医療従事者2,370人のうち,91%に当たる2,168人が被爆した。彼らは自ら傷を負いながら,救護に立ち上がった。限られた医薬品で負傷者の治療に当たる一方,「原爆症」という人類未知の病気にも手探りで取り組んだ。日々,被爆者と接し,有効な治療方法を忍耐強く模索し続けた広島の医師たちの情熱と努力の積み重ねが,昭和31(1956)年9月の原爆病院の開設に結びつき,被爆者医療の発展を促した。市内中心部の平和大通り沿いにたたずむ「原爆殉職碑」,昭和35年8月に広島市医師会が建立した別名「祈りの手」は,そんな医師たちの苦闘の歴史を今も静かに伝えている。
(永井 均)
注・参考文献
1)中沢啓治『はだしのゲン』第2巻(汐文社,1975 年)40 頁。
2)広島原爆障害対策協議会編『広島原爆医療史』(広島原爆障害対策協議会,1961 年)9- 11 頁。
3)蜂谷道彦日記,昭和 20(1945)年8月7日条(蜂谷道彦『ヒロシマ日記[新装版]』法政大学出版局,2003 年)19 頁。
4)前掲『広島原爆医療史』9- 10 頁。
5)同前『広島原爆医療史』144 – 148 頁。広島原爆障害対策協議会編『被爆者とともに―続広島原爆医療史』(広島原爆障害対策協議会,1969 年)50 頁。
6)同前『広島原爆医療史』13 頁。蜂谷道彦日記,1945 年8月7日条(前掲,蜂谷『ヒロシマ日記[新装版]』)11 頁。
7)重藤文夫・大江健三郎『対話 原爆後の人間』(新潮社,1971 年)87 頁。
8)蜂谷道彦日記,昭和 20(1945)年8月 12 日条(前掲,蜂谷『ヒロシマ日記[新装版]』)64 – 65 頁。
9)前掲『広島原爆医療史』323 頁。前掲,重藤・大江『対話 原爆後の人間』46 – 47,53,72 頁。
10)大江健三郎『ヒロシマ・ノート』(岩波書店,1966 年)132 頁。