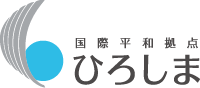Leaning from Hiroshima’s Reconstruction Experience: Reborn from the Ashes vol3おわりに
「ひろしま復興・平和構築研究事業報告書」として平成26 (2014)年に刊行された『広島の復興経験を生かすために』で、筆者は「原爆報道」「市民生活の再建と変遷」を概述した。「原爆孤児」をめぐる軌跡には言及しなかった。紙幅に限りがあったとするのは言い訳だろう。沈黙を押し通す人たちが、はき出す言葉に出会うたび打ちのめされ、軽々しく述べる立場にないと思ったからである。
今回、執筆に応じたのは、これまでの史誌で扱われていなかったり、見過ごされたりしてきた記録をとどめたい、それ以上に、「原爆孤児」と呼ばれた人たちの言い尽くせぬ一端を伝えたいとの思いからである。自省を込めて記すがメディアは、進んで語ろうとしない人たちの原爆体験を取り上げなくなった。
15歳の夏に被爆し、両親と姉を奪われ、広島一中(現国泰寺高)を卒業すると原爆を投下した母国へ「生きるために」帰った日系 2世の言葉を最後に紹介したい。カリフォルニア州で農園季節労働者となり、陸軍にも勤めた。知己を得た日系2世は今、広島市に住み、平和記念公園へ墓参として足を運ぶ。かつての住まいは原爆慰霊碑近くにあった。
「米国でくじけそうになると、両親が夢枕に立ちました。父と母を合わせた年齢まで生きようと思ってきた。それを超えたけれど、私の心の平安は、両親のもとへ行ったときでしょう」。穏やかな口調でそう語る。
広島は廃虚から「復興」を成し遂げ、発展した。市民・県民のたゆまぬ営為で119万都市となった。しかし、原爆の悲惨を生き抜いた人々がいたことや、語られない思いがあることは、どこまで意識されているだろうか。自身が亡くなって「平安」を得られるという、すさまじい言葉に触れると、人間の「再生」は重く耐えがたいものとしか言いようがない。戦争・原爆が、それを強いたのである。