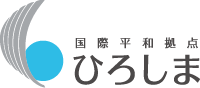Leaning from Hiroshima’s Reconstruction Experience: Reborn from the Ashes vol36 語られざる軌跡
「地下室の奇跡」。広島市中区の袋町小平和資料館が展示しているパネル説明である。爆心地から約460メートル。焼け残った鉄筋西校舎の一部を市が保存して平成14(2002)年に開館した。地下室で被爆した3人の児童が助かったことを「A」「O」「T」と報道を基にイニシャル表記で伝える。
しかし、昭和20 (1945)年8月6日の「奇跡」の後はどうなったのかは触れていない。3人はいずれも「原爆孤児」となった。本人や遺族への筆者のこれまでの取材や提供された資料を基に記す。
4年生だった「A」は、父の病死に続き、原爆で母や祖父母、きょうだいの家族 8人を失った。松江市に住む父の妹に引き取られ、中学を卒業するとすし店で住み込み修行をした。義父となる店に勤めて独立し1男 1女をもうけたが、胃がんのため平成5年に57歳で亡くなった。
原爆関連のテレビ番組を見ると「あんなもんじゃなかった」とは吐露しても、妻や店を継いだ長男にも自らの体験を詳しく語ろうとはしなかった。
「A」の手を握り脱出した級友「T」の半生は、流転の半生となった。一緒に登校した弟(当時8歳)は死去。病死の父に代わって洋服仕立てをした母(同30歳)は見つからず、下宿していた朝鮮半島出身の男性と再会する。一緒にバラック暮らしを始めたが昭和20年9月17日の枕崎台風で押し流され、その男性とソウルへ。駐留米兵相手に靴磨きをし、路上でかますにくるまって寝た。砲弾が目の前で飛び交う朝鮮戦争も体験した。パン製造店に住み込んだ20歳のころから政府やソウル市を訪ね、帰国を訴えたが、門前払いが続いた。国交がなかったからである。
「故郷ガナツカシクテ」。戸籍謄本を求める手紙が昭和33年広島市に届き、ソウル市長の協力もあり国交回復前の35年6月、念願の帰郷にこぎつけた。日本語はすっかり忘れ、手紙は「息子同然にかわいがってくれた」婦人が書いてくれた。広島市の紹介でようかん製造店に勤めたが、「どうしてもお母さんや弟がいたころを思い出して…」。帰国が騒がれた分、好奇の目でもみられた。在日韓国人のつてを頼って大阪へ移り、30歳の年に結婚。転職したステンレス加工会社で働き、4男1女を育て上げた。落ち着いた生活を手にしてからは渡韓を重ねて「恩人」の婦人を捜した。現地のテレピ番組で呼び掛けた1995年、亡き婦人の長女との再会を果たした。最愛の妻を平成25(2013)年に亡くし、再び一人暮らしとなったが、大阪府内で健在である。今年82歳となる。
「O」は2年生だった。父(当時45歳)と母(同44歳)やきょうだいの家族 6人を原爆で失った。学童疎開先から戻った兄や姉と別れ、広島県戦災孤児教育所似島学園へ預けられる。連合国軍総司令部(GHQ)の占領統治が明けた昭和27年8月6日、広島市の平和記念式典で、原爆慰霊碑を除幕した児童・生徒 5人の1 人となり、兄の支援で高校を卒業して大阪の写真学校へ進んだ。広島市内で写真現像店を営み、39年に結婚。新妻を寺町(現中区)の菩提寺へ伴い「両親の墓」を紹介した。店の賃貸し契約が切れたのを機にタクシー運転手に転じたが、体力的に続かなかった。34歳の年に市職員に採用され、息子2人が生まれると自宅も構えた。しかし平成 3年、胃がんが見つかり全摘手術を受ける。
「話したところで今さらどうなるわけじゃなし」。ヒロシマ50年の企画取材に、ためらいながらも応じた。原爆慰霊碑を一緒に除幕したのは、親を失った子どもたちだった。「どうしているのかな」「いや、向こうも会いたくないでしょう」と自問自答した。記事を見た袋町小の要請で児童らに自らの被爆体験を語ったが、メディアには再び出ようとしなかった。平成19年に70歳で亡くなった。
妻を訪ねるとこう語った。「息を引き取る3カ月前から、避けていた孤児のころのことも勢い込んで話しました。まさか死ぬとは思えず、もっと聞いておけばよかった…」。心の整理をつけることに最期まで苦しんだのだろうか。
原爆後を支え合いながら、日本と南米ブラジルで生き別れとなった兄弟の軌跡についても触れる。生家は旧材木町の石材店、現在は原爆資料館が立つ。
兄は市立第一工業学校(被爆後に廃校)1年生だった。建物疎開作業に動員された鶴見橋近くで被爆した。母(当時35歳)と弟妹の4人が死去し、三良坂町に集団疎開していた中島国民学校4年だった弟の2人となった。父は病死し、東千田町(現中区)に住む母方の祖母を頼るしかなかった。兄は学校をやめて市内の建具店に住み込む。弟は翌年に祖母宅を飛び出し、広島駅をねぐらにしていたところを見つかり、県戦災児教育所似島学園1期生34人のひとりとなった。
兄は弟を手紙でも励ました。「この間会った時にお前に気にくわぬことを言ったが、許してくれ/だが、気の持ちようだ。しっかりやれ。前を見て進め。人に負けるな。頑張れ」。弟は学園の紹介で加計町(現北広島町)の農家で働き、 24歳となった昭和34年、ブラジルへ単身渡る。地元青年団の壮行会にも兄も出席した。それが兄弟の別れとなった。
広島県知事大原博夫は昭和31年、米国に続いて、ブラジル各地を 2カ月に及んで回り、「呼び寄せ移民」への協力を求める。復興途上の広島市や県内農村部の次男・三男の就労の場を広げようとした。広島は戦前に全国最多の移民を送り出した「移民県」でもあった。ブラジルでは推計5500家族からなる広島県人会が前年の1955年に結成されていた41。
弟は、甲田町(現安芸高田市)の出身者が開拓するサンパウロ州の農場に入った。約7ヘクタールの畑を馬でも耕し、夜は鶏舎を回り、土曜日は市場で野菜を売った。渡航11年後、「パトロン(農場主)」の末娘と結婚し、2児の父となった。しかし、日系2世の妻にも「兄がいる」と言うだけで広島には触れたがらず、挙式を知らせた加計町の知人とも連絡を断つ。1986(昭和61)年に51歳で死去した。
サンパウロ市内に住む妻を後に訪ねると、「夫は『広島へ帰るくらいならブラジルを旅行する』と言いました。でも、原爆の日は必ずこちらのお寺にお参りしていました」と話し、夫の墓に案内してくれた。原爆の忌まわしさを振り払おうとしたのか、浴びるほど酒を飲んだという。
「爆心の兄弟」を追ったのは、妻が「夫の死を兄に知らせてほしい」と、ブラジル広島県人会の理事に代筆を依頼した手紙を受け取ったことから。兄の名前も住所も分からなかったが、原爆前は「材木町」で暮らしていたとあった。ゆかりの人たちや親族を訪ねると、兄は昭和48年まで広島市内で働き、腕利きの建具職人だった。しかし、子どもができなかったことや深酒が重なり家庭は破綻し、行方知れずになったという。
ようやく捜し当てた兄は、西日本最大の日雇い労働者が集住する大阪市西成区の「あいりん」地区にいた。54歳だった。
「弟はブラジルで元気にやっとると思ったけどな…わしも金を稼いだら行くつもりじゃったが、いろいろあったし・・・」。酒場でむせび泣いた。関西の建設現場を転々とし、「あいりん」に住民票を移していた。「仕事中に目をやられ、手配師が安う診てくれる病院を世話してくれたんや」。被爆者健康手帳は取得していなかった。酔いが進むとこうも明かした。
「わしが原爆手帳を取る気がないのを知り、『戸籍を売れば金になる』と言うやつもおった。原爆がついて回る広島におるのがいやになった」。亡き弟の名前の一文字になぞらえて、「弟は幸せだったと思う。おりとうなかった日本を出て、子どもにも恵まれた。ブラジルのおいが17代目か…」と忍んだ。写真をブラジルに送ってくれと、通天閣を背にポーズを取った。「爆心の兄弟」と題した連載記事を機に広島の親族と連絡をするようになったが、やがて音信を再び断った。健在であれば今年85歳となる。
41 ブラジル広島県人会編『ブラジル広島県人発展史並びに県人名簿』(ブラジル広島県人会,1967年)38頁