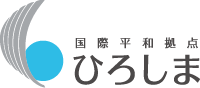column 4 映像に見るヒロシマ
柿木 伸之
はじめに
「きみはヒロシマで何も見なかった」。被爆地広島を舞台にした映画として世界的に最も知られている作品の一つ,アラン・レネ監督の『ヒロシマ・モナムール』(昭和34[1959]年)の冒頭のシーンで,建築家の男は,広島で彼と恋に落ちたフランス人の女優にこう告げる。「私はすべてを見た」という彼女の言葉を遮るように。
「きみはヒロシマで何も見なかった」。この言葉は,ヒロシマを撮った映画からも聞こえてくることがある。その映像の細部は,あるいはドラマの機微は,見る者を未知のヒロシマに出会わせるのだ。ここでは,それによってヒロシマの記憶を絶えず更新させる力を具えた映画のいくつかを紹介することにしたい。
1.記憶の邂逅とリアリズム
日本では『二十四時間の情事』という表題で公開された『ヒロシマ・モナムール』には,原爆によって家族を失った建築家と,敵国の兵士と恋仲になったためにフランスの人々に糾弾された過去を持つ女優とが,心に傷を残す記憶を交わし合うさまが,昭和33(1958)年の広島の街とともに繊細に描かれるが,そこにはヒロシマの記憶を世界的な文脈で捉え返す糸口も示されていよう。また,この作品には別の映画から,原爆投下直後の広島の地獄図を映す映像が引用されている。その映画とは,関川秀雄監督の『ひろしま』(昭和28[1953]年)である。
占領軍によるプレス・コードが昭和27(1952)年に解かれてからほどなくして,原爆をテーマにした映画が日本国内で作られ始める。『ひろしま』は,新藤兼人監督の『原爆の子』(昭和27年)に続いて作られた,最初期の原爆映画の一つである。『ひろしま』において特筆されるべきは,9万人に及ぶ広島市民をエキストラに動員し,徹底的なリアリズムで被爆の惨状を描き出している点であろう。その衝撃力は今も色褪せない。
2.復興の中の「原爆の記憶」
1960年代に入ると,復興が進む広島の街とともに,原爆の記憶を抱えてそこに生きる人々の姿に目を向けた映画が生まれている。なかでも吉村公三郎監督の『その夜は忘れない』(昭和37[1962]年)は,被爆の傷を隠しながら歓楽街に生きる一人の女性の心情の機微を,印象深く伝えている。ヴェトナム戦争下の状況に広島を置く白井更生監督の『ヒロシマ1966』(昭和41[1966]年)は,原爆で夫を失った女性とその娘が,困難な状況を生き抜こうとするさまを,当時の街の周縁とともに描いて忘れがたい。昭和48(1973)年から翌年にかけて広島を舞台に撮られた深作欣二監督の『仁義なき戦い』5部作は,アウトローな人々の群像劇の中に復興の暗部も映し出している。
おわりに
比較的最近の映画では,井伏鱒二の小説にもとづく今村昌平監督の『黒い雨』(平成元[1989]年)が,原爆症への不安を,福島第一原子力発電所の重大事故後に生きる者に深く訴える作品として見直されるべきであろう。それ以後もヒロシマの映画は作られ続けている。なかでも,平成19(2007)年に『ヒロシマナガサキ』を公開して,全米に被爆者の証言を届けたスティーヴン・オカザキがそれに先立って撮った『マッシュルーム・クラブ』(平成17[2005]年)は,原爆の傷を抱えながら生きる人々の姿を,今の広島に細やかに浮かび上がらせる。こうした映画を通じてヒロシマに出会い直すことは,被爆の記憶を更新し,復興史を捉え直しながら今を見つめ直す,かけがえのないきっかけになるはずである。